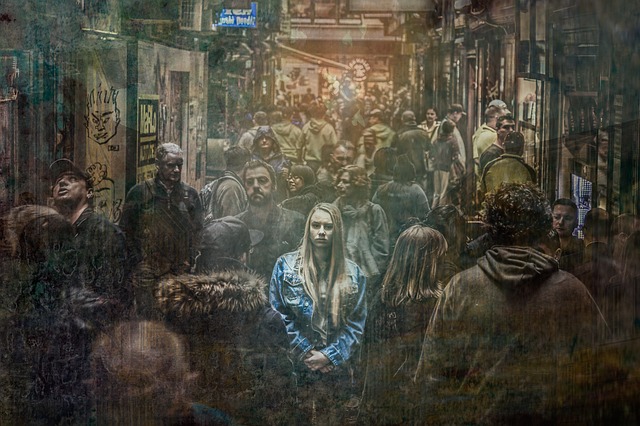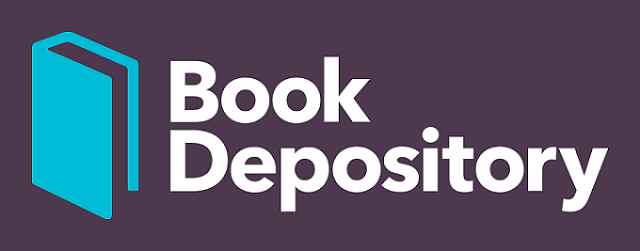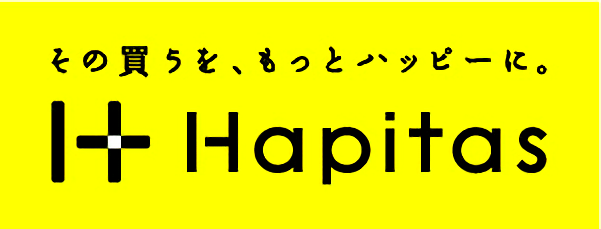僕は、「人は生まれながらにして一定の権利を持つ」(自然権)という“言説”に対して「なぜ?」と疑問を持つことのできる人が好きですし、その疑問に対して「そういうことにしておくことが社会には必要だから」と、まともな答えの出せる人が大好きです。
— 佐脳FRAN (@F_Sano_) 2018年2月18日
自然権が「あるとする」ことは別に構わないんですよ。
ただ、「自明に存在しているもの」であるかのように、無思考でそれを受け入れている人があまりに多いように思うのです。
そして、そういった人はまるで「お人形さん」のように見えて、(私には)気持ち悪いのです。