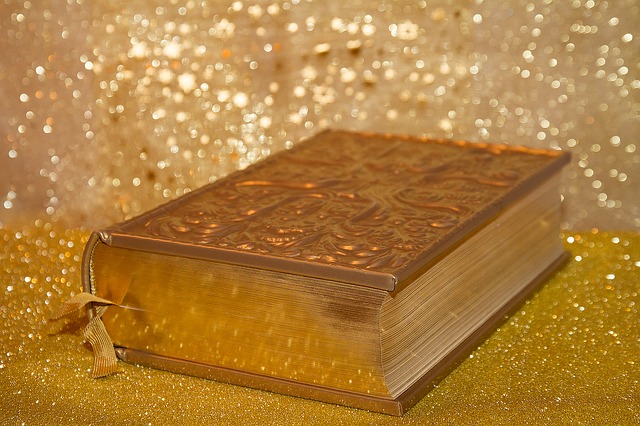dlitさんのコチラの記事
を読んで、大学生(学部生)の頃に言語学関連の本を読んでいた際の、楽しかった記憶が甦ってきました。
……といっても、私は言語学科にいたわけでも、人文学部にいたわけでもなく、法学部の政治学ゼミに所属したんですよね。
そんなやつがなぜ言語学の本なんて読んでいたかというと、
・人の活動の多くが言語をベースにしているのであれば、それ(言語)についての理解がなければ、そもそも政治学なんてできないのでは? という疑問(気付き)を持った
というのが、主な理由です。
(残念ながら、私には“まともに”政治学をやる能力はありませんでしたが…)
言語学と政治学が明確にリンクしている(当時の)既存の学問領域というのはかなり少なく、卒業研究にかなり苦労することになるのですが、それでも私にとって言語学というのは非常に興味深いものでした。
特に、人の認知、思考と言語の関係性、社会・文化と言語の相互関係というような内容は、法学部の政治学ゼミに身を置く者としては大変面白く、その辺りに関する言語学の知見を得ていくのが純粋に楽しかったことを覚えています。
……というようなことを思い出しながら、この記事では当時私が読んだ言語学関連の本の中から、言語(学)に興味を持っている他学部の学生や、社会人の方にオススメの本をいくつか紹介したいと思います。
手に取りやすいよう、新書・文庫が中心です。
ぜひ参考にして、言語(学)の面白さを味わってください。
①鈴木孝夫『ことばと文化』
ド定番中のド定番。まず最初に読むべき本。
「言葉ってそもそも何なんだろう…。人とどう関係しているものなんだ…」と、言葉について漠然とした疑問を抱えている人は、得るところが非常に多いはず。
今読み返してみると、なかなかに広く深い内容が実に平易述べられていて、感心しきり。
未読の方はすぐに読むことをお勧めします。
②町田健、籾山洋介『よくわかる言語学入門 解説と演習』
『ことばと文化』などを読んで言語学について興味を持ったら読むとよい本。
日本語教師用の本ですが、言語学の“スタンダードな”領域を広くカバーしており、内容も分かりやすく、良質な「言語学の入門書」になっています。
200ページもない薄さも、初学者には嬉しい。
参考までに目次を挙げておきます。


さっと一通り読んで、言語学の基本的な知識を身につけると共に、「特に自分が関心のある領域」を探す使い方をするのがお勧めです。
なお、「『ことばと文化』の次は、『言語と社会』じゃないの…?」と思った方は、最近の「面白い」言語学関連の本(一般向け)を教えてください。
③ 加賀野井秀一『20世紀言語学入門』
②のような平易な入門書を読んだ後、ソシュール以降の言語学の展開を押さえておきたと思った場合にオススメの本。
ソシュール、構造言語学、構造主義、記号論、チョムスキー、語用論、発話行為論など、いくらでも難しい内容をかける領域が幅広く取り上げられていますが、予備知識がなくても読めるくらいに巧く噛み砕いて説明がされています。
④入谷敏男『ことばの心理学』
「人の言葉は動物や機械のそれとはどのように違うのか」と疑問に思う人や、「言語の機能」に関心を持つ方にオススメ……なのですが、絶版。(私が初めて読んだ当時も絶版でした)
ただ、中古でなら安く手に入りますし、「言語と心理」の領域についての本は、新書や文庫といった「一般向けの、低価格帯でページ数の少ないもの」が(おそらく今も)少ないと思われるので、関心がある方にはオススメです。
(入谷敏男の本は面白いものが多いので、気に入ったら他の本も読んでみてください)
⑤今井むつみ『ことばと思考』
これまでの言語学の領域に認知科学的手法を取り入れた、割と新しい分野についての一般書。
内容としては、①②④の本などでも取り上げられているような、従来の言語学で扱ってきたものがほとんどですが、それを認知科学的な視点で見た際にはどうなるなのか、という点が興味深い。
言語と認知、思考の関係に関心がある方や、これまで挙げたような本を読んだ際に「言語学の内容は面白いけど、それってどれくらい証明できるものなの?」と疑問を持った方にオススメです。
⑥加藤秀俊『人間関係』
社会学の領域に属するであろう本ですが、3章の「ことばと人間関係」が面白い。
そこで示されているコミュニケーションモデルによって、人がいかに会話によって相互にオーバーライトされていく存在であるかを理解した際、私は吐き気さえ感じたものです。
人間と言語的(バーバルな)コミュニケーションの関係について興味がある方にオススメ。
⑦塩見鮮一郎『差別語とはなにか』
差別用語は、「差別」について考える際に重要な題材であるだけでなく、言語について考える際にも重要な題材になります。
というのも、用語の使用・不使用について何らかの(広い意味での)力が働くということは、人の多くの活動の元となる言語に力が働いているということであり、そのような力の構造を知ることは、人の活動への理解を深めることにもなるのです。
(具体的には、単語と指示対象(指し示すもの)の関係、単語による分節とアイデンティティ、言語規則は社会規則であること等々を、実際に起きた事例を通して理解することができます)
本書は、この手の本でありがちな「憎悪」が薄いので読みやすく、また、筒井康隆とてんかん協会との間で起こった問題を中心に、実際に起こった差別用語問題の(一部の)流れを分かりやすくまとめているので、1冊目として読むのにオススメです。
⑧金水敏『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』
中国人キャラは「~アルヨ」、老人・博士系のキャラは「~じゃ」、お嬢様キャラは「~てよ」(例:よろしくってよ)等々、特定の属性を持つキャラクターが話す特定の用語や語法、それが「役割語」です。
本書では、その役割語についての歴史から、実際に使うような人物はまずいないにも関わらず、なぜ「それらしく」思えるのかといったことまで、なかなか幅の広い内容が平易に述べられています。
個人的には、役割語が生れる前提となる「標準語」がいかに誕生したかの話が特に興味深かったですね。
現実的ではないのに日頃よく目にし、耳にする役割語。
興味を持った方はぜひ一読を。
・おまけ
「言語学関連の入門書」と言うにはちょっと内容が離れすぎていたり、敷居が高いかもしれないけれど、面白いので興味があれば読んでもらいたい本。
(1) 杉田敦『境界線の政治学 増補版』
言葉による分節(切り分け)の力が政治学的な視点から述べられている本。
今は文庫で読めるのですから、実にいい時代になったものです。
(2) メアリ・ダグラス『汚穢と禁忌』
こちらは言葉による分節の力が、文化人類学的な視点(タブー論)から述べられている本です。
文化人類学の本の中では一番のお気に入り。
(3) 小林健治『差別語・不快語』
「憎しみ」なしに、幅広い差別用語の事例が詳しく取り上げられている貴重な本。
コラムの内容も興味深いものが多いので、塩見鮮一郎『差別語とはなにか』などから差別用語に関心を持った方は、ぜひ一読を。